紅、流れる 薄暗い空に灰色の雲が斑をえがいている。天が崩れて今にも落ちてきそうだ。自分が逝く場所はそこにあるのだろうか。仰向けの幸村は息を切らして思った。 腹から血があふれて止まらない。鼓動が地面を伝ってどくどくと耳へ届く。伸ばしきった指先はまだ動いた。傷口に触れ、渾身の力で炎を宿す。 咽喉まで焦がさんばかりに絶叫した。肉の焼ける臭いが漂う。 これでわずかでも存えるだろう。しかし全身は重いのか軽くなっていくのかさえ曖昧だ。 伊達政宗の六爪は比類ない威力で二槍を削り、ほとばしる稲妻は両腕を痺れさせた。おのれは、負けたのだ。西と東による天下分け目が、好敵手との雌雄も決めるだろうと、承知していなかったわけではない。改まった舞台で決着を望む幸村にとって本懐から外れていただけだ。 東軍として政宗が石田三成を狙う限り、阻止せねばならなかった。三成の目的は徳川家康を討つことだ。西の盟約はその為のものである。願わくは自らの手で政宗も、家康も越えたいが、大いくさとなった関ヶ原の地で、一将が私欲で敵を選るなど有り得なかった。 幸村は身体から満遍なく感じる痛みに息を吐き続ける。離れた場所から無数の矢が飛んできた。避けることもできず四肢に浴び、そのたび呻く。 負けた悔しさと、空しさが渦巻いている。川中島で政宗が「顔をあわせたときが、戦りあうとき」と言い放ったことがある。対峙する心は決めていた。乱世に生きるならば、いのちは常に懸けるべき焔だ。敗北は死を意味してもおかしくない。当たり前の覚悟であったのに、ここで果てれば一体なにを残すというのだろう。 幸村は知っている。家康にも虎の魂がある。おのれの器は日ノ本統一を志した師ほど大きくない。ただそんな自分でも、武田を治める頭として、この先の未来を築こうと思う。なにもかもと向き合うべく就いた西の地位だ。役目さえ全うできなければ水泡となる。 幸村は、叫ぼうと口をあけた。奥でつかえ、声にならなかった。 力が抜け、ぐったりとまぶたを閉じる。足音が近づいてきた。兵が、とどめを刺しに来たのかもしれない。 「おい」 低い声だった。かろうじて目をあける。幸村の視界に、ぼんやりと人影が浮かぶ。鼻梁の前でまとめられた銀髪、細身の体躯は長刀を腰に提げず手で持っている。三成だった。ところどころ鎧が砕け血を流し、肩で息をしている。 「何ゆえ、貴殿がここに」 かすれていたが、確かに響いた。三成は答える。 「すべて終えた」 吊り上った両眼は、うつろだった。静かに佇み、幸村を見下ろす。 「家康はもういない」 透明な声音は、ひとり言のようにきこえた。しかし幸村は、いちばんの懸念を問う。 「政宗殿は」 「手負いの竜など足らぬ相手だ」 そうでございますか。消え入りそうに震え、つぶやいた。大将が勝利し、直々に伝えに来たというのに、歓喜とはほど遠い。 幸村は首だけを傾ける。 「三成殿、お顔についているのは、血水ではありませぬか」 起き上がろうと試みたが、もう指先も動かなかった。 「拭うこともできぬなど、まこと役に立ちませぬな」 途切れ途切れにこぼす。三成は唇を噛み締め、そっと歩む。 「黙れ」 刀の柄を向ける。 「私が聞きに来たのは、そんな言葉ではない」 わずか離れた背後に、黒い羽根が舞った。佐助だった。忍び衣装が破れ、傷だらけである。武田信玄が倒れて以来、陰の采配のみならず、表立った場で戦力の不足を補ってきた。 眼前であるじが倒されようと加勢せず、三成へ伝えに駆けた。おのれの大将が命を懸けて盾となったのだ。西という巨大な軍に属し参じている以上、武田ではなく、忍びとしての矜持を守らねば、にわか頭の体面も、甘えを捨てようとしているあるじの覚悟そのものさえ潰すだろう。 しかし、断腸の涙を殺しているのは、歪んだ表情から見てとれる。佐助は腕の傷口を押さえ、苦しげにこちらを眺めている。周囲の地面は赤黒く変じ、腹には爛れた生々しい痕がある。 もう助からない。 幸村は大きく息を吸った。 「無二の好敵手、忍びと師に恵まれ、幸せにござった」 三成は苦々しく吐いた。 「貴様の目指すものすべて、私が討ったこの終幕もか」 「総大将殿に見送られることもまた、天命なのであろう」 勝利して逝けるのだ。ただおのれがその為に、なにを成せたのかが知りたい。家康と政宗を越える目的をなくして今、三成の空漠も埋められず、盟友の奥底ひとつ分かちあえないから、尚更うら悲しいのかもしれない。 「来世は貴殿とも手合わせを」 銀髪の奥で鋭眼が凄む。 「生まれ変わりなどあるならば、私はとっくにこの憎悪を棄てていた」 時間は戻らず、死すれば、さらに取り返せるものはない。罪を受けるのも、罰を与えるのも、すべて今でなければ意味がない。 だから生き続けているのだ。三成がそう言うと、幸村がほほ笑んだ。 「いつかおっしゃいましたな、死は裏切りに値すると」 「そうだ」 「お怒りにならぬのですか」 この御方は静かなひとであるけれど、感情を殺すのは得意でないはずなのに、と幸村は思う。 「そこの忍びに免じている」 三成は冷ややかに告げる。 「あるじを抱え逃げることもなかったのは、貴様の誓いを破らないためだ。その結果を、斬るつもりはない」 ゆえに問う、と続ける。 「私を裏切り、野垂れ死ぬのではないな」 白皙の厳しい顔つきが、壊れてしまいそうなものに見えて、幸村は翳み出した視界のせいだと思った。返す言葉に、力がこもる。 「無論」 「秀吉様に誓えるか」 「いいえ」 目をとじた。全身から力が抜ける。何も残らない、など、それすら驕りだったのかもしれない。最期まで未熟だ。たくさんを、遺して逝く。真正直に生きた果てならば、貫いてこそ悔いもない。 「貴殿と、某の忍びに誓いましょう」 武田の将と、真田幸村としての魂を同時に抱えて逝ける。幸村はまぶたを上げずに息を吐いた。 三成の大きくひらいた両眼を、認めることはなかった。 明度の落ちた空からしずくが降る。地を濡らし、湿った香りが漂い始める。赤い装束が身じろぎひとつしない横で、三成は立ったまま天を仰いでいる。 「あの日も、雨が降った。遺言など聞けぬまま」 佐助の位置から、銀髪の下は窺えなかった。三成は続けた。 「貴様には礼を言ってやる」 ぽつぽつと、水しぶきが舞う。衣服と肌についた血が滲み、流れて道をつくる。佐助が覇気もなくつぶやく。 「勝ち鬨を上げてくれよ、大将」 2010/11/24 いい西の日。 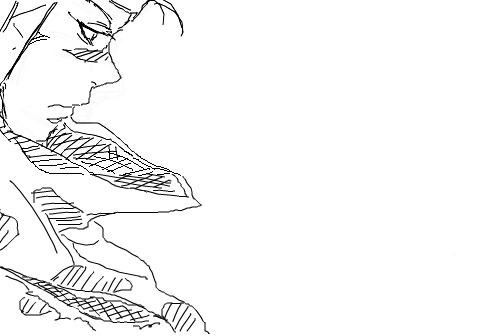  |